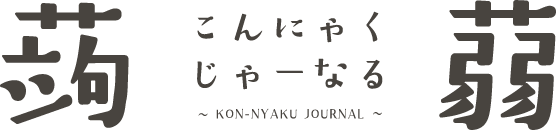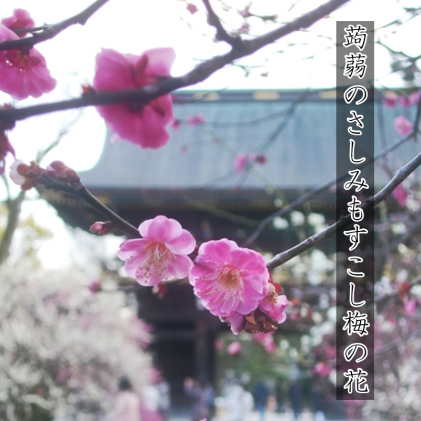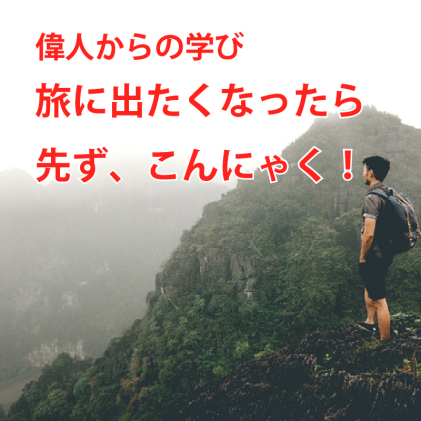[偉人(かも?)と蒟蒻]
松尾芭蕉&蒟蒻俳句
こんにゃくと関係が深い偉人をフィーチャーする本シリーズ。今回は日本各地をハイクして(歩いて)、俳句を詠んだ、江戸時代の「俳聖」、松尾芭蕉です。実はこの方、大のこんにゃく好きで、俳句の中にこんにゃくを登場させちゃう程なんです。
こんにゃくの さしみもすこし 梅の花
【訳】(仏前には)こんにゃくの刺身が、少し供えられている。(寺の庭には)梅の花が咲いて春はもう近い。
去来というお弟子さん宛に、共通の亡き知人のことを悼んで送った句です。佗しい芭蕉の生活の一端と、亡き人への思いやりの心に、ほのぼのとする一句です。また、こんにゃくのグレーと、梅の花のピンクが対照的で、視覚的に面白い句になっています。
こんにゃくに 今日は売りかつ 若菜かな
【訳】いつもならこんにゃくがよく売れるらしいのに、さすがに七草粥を炊く正月七日の今日は、若菜のほうがこんにゃくより、よく売れているようだ。
この句から現代と同様、当時もまた、こんにゃくが皆に人気だった事が分かります。そして、芭蕉が常にこんにゃくを気にしていた事がうかがえます(笑)。最初、この句に登場したのは、ハマグリだったのですが、決定稿はこんにゃく。さすがは芭蕉殿、こんにゃくびいき♡
当時の江戸の俳諧は、華々しい派手な俳句が流行っていましたが、芭蕉がテーマにしたのは、静寂の中の自然美や人生の探究です。“侘び・さび”の精神が効いた句は、現代の私たちの心にも響きます。贅沢はせず、うわべだけの名声を嫌った彼の性分と、派手さはないが美味しいこんにゃくは、とても相性が良かったのかもしれません。
また、「奥の細道」でも知られるとおり、大の旅行好きでもあります。道中で残した名句もさることながら、その健脚たるや目を見張るものがあります。実は忍者だったのではないか、という噂も出るくらいです。
そんな長旅を支えたのは他でもない、我らがこんにゃくなのです。
日頃からこんにゃくを食べていた芭蕉は、腸内環境のバランスはバッチリ〇、グルコマンナンのダイエット効果で体重も軽かったハズ。皆さんも長旅の前には、こんにゃくで腸内環境と体重を調整し、身体(特にひざ)に負担ない、楽しい旅行にお出かけください。
■おまけ■
あらたふと 青葉若葉の 日の光
【訳】ああなんと尊いことだろう、「日光」という名の通り、青葉若葉に日の光が照り映えているよ。
芭蕉はワタクシが住んでいる日光にもおいでになり、上の名句を詠まれました。もしかすると、東照宮に行く道中、我が家の前も通ったかも知れませんね(笑)。