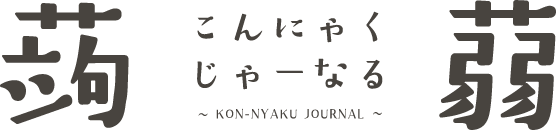[ぷる×2系 パワスポ]
もうひとつの“蒟蒻神社”
こんにゃく関連のパワースポットを巡る、本シリーズ。今回の目的地は千葉県船橋市飯山満町(はさまちょう)にある大宮神社、通称“蒟蒻神社”です。
こんにゃく じゃーなるの熱烈な(?)ファンの皆さんなら、「蒟蒻神社って、茨城県大子町にもあったよなぁ。」と思ったはず。そうなんです!実は茨城県大子町とは別に、“もうひとつの蒟蒻神社”が千葉県にあったのです。
同社の創建は中世とされ、御祭神は、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した素盞嗚尊(すさのおのみこと)。この地は昔から蛇が多く、里人を苦しめたことから、祀り上げたようです。
毎年、1月7日と10月23日は祭礼で、神楽(かぐら)が舞われるようなので10月(2016年)のこの日を狙って、行ってきました。
なぜ?“蒟蒻神社”と呼ばれるのか!?
明治時代にこの周辺の村々で、盛んにこんにゃく芋の栽培が行われたことに由来するそうです。事実確認のため、祭礼の準備をしていた氏子の方にお聞きしたところ、「えっ!?こんにゃく?初めて聞いたよ。何世代も昔は作ってたかもな〜。」といった感じでした。もっといい反応が返ってくるかと思ったのですが…(汗)。今ではこんにゃく芋は、ほとんど作ってないのだとか…なんとも残念。
“蒟蒻神社”の認知度が低くても
栽培に適した地形
実際に飯山満駅から同社まで歩くと、急な登り坂が多い事に気付きます。この辺りは高低差が激しい地勢。土地に傾斜が付いているという事は水はけが良く、こんにゃく芋の栽培に適しているという証です。現在は閑静な住宅地ですが、ふと歩みを止めて辺りを見渡すと、かつて広がっていたこんにゃく畑が眼に浮かぶようです。
船橋市の指定無形民族文化財
飯山満町大宮神社 神楽
陽も落ちかけた夕方5時、伝統的な神楽が厳かな雰囲気で始まりました。古くから農業が盛んであったこの地で、五穀豊穣を願い、豊作に感謝するものとして、後世に伝えられてきました。その歴史は古く、江戸時代末頃には既に演じられていたそうです。
笛・大太鼓・小太鼓が演奏され、様々な衣装による舞いが披露されます。現在伝えられている演目は12座で、そのうちの「神功皇后(しんぐうこんごう)」*が舞われるのは、市内で同社だけとか。これは一見の価値アリです。
今回は飯山満町大宮神社、通称“蒟蒻神社”にお邪魔しました。鳥居をくぐり、参道を歩いていると、少し寂しげで、何とも言えないノスタルジックな感じがしました。
同社の周りは、農村から住宅地へと変貌を遂げていますが、境内は古き良き日本がそのまま残っているかのよう。「こんにゃくに縁ある所、懐かしき風土あり」ですね。
ご利益は厄災除け、病魔退散、産業振興との事です。是非、年二回の祭礼を狙って、参拝したいものです。
*【神功皇后(170~269年)】
記紀(古事記と日本書紀)に登場する天皇のきさき。三韓征伐(朝鮮半島南部)に自ら兵を率いたと記述があるが、神話上の人物とみられている。