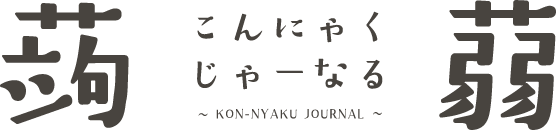[ご当地 美味 を訪ねて]
節分けんちん、知ってる?
“節分フード”といえば、真っ先に挙げたいのが「豆」。昨今ではコンビニでも売られるほどの定番品となった「恵方巻」も、国民的節分食です。
そして、我らが愛する「こんにゃく」も、実はご当地によっては節分フード!? 今回は、“節分こんにゃく”の謎に迫ります。
「節分」は、冬至・春分の中間にあたる立春の前日。歴のうえでは、“立春=春のはじまり”。節分は、季“節”を“分”けると記す通り、冬→春の変わり目にあたるんです。
季節の変わり目には邪気が生じると昔の人は考え、その邪気(鬼)を追い出すため、「鬼は外〜」と豆を撒くようになったみたい。一説によれば、豆は“魔滅(まめ)”に通じるからなんだって。
煎った大豆を使う地域が大半ですが、北海道・東北・信越地方、九州の一部では、大豆ではなく落花生を使用するそう!

イワシは古くから
全国的な節分フード。
理由は「鬼が嫌うから」。
恵方巻の起源は諸説あるものの、もともとは大阪の花街で縁起を担いで食されていたもの。地域ごとの特色がある節分フードですが、共通しているのは「厄除け・魔除け」「開運」といえそうデス。

四国では、白あえ・煮しめで
節分こんにゃく?!
で、節分にこんにゃくを食すのはドコかというと……。
1つ目は四国地方。食べ方は、白あえや煮しめとの噂(※)。江戸時代より「こんにゃくはお腹の砂下ろし」なんて言葉があるわけですが、これは、こんにゃくの食物繊維が腸を掃除してくれることから。そこで、節分=季節の変わり目にこんにゃくを食すようになった模様。
お腹スッキリ=デトックス♥ 節分にこんにゃくを食せば、心身ともにスッキリ状態で新しい季節を迎えられる……ということなのデショウ。
※噂のモト:中国四国農政局ホームページ

関東は、けんちん汁を節分に?!
2つ目の地域は、関東です。古くから、関東地方の一部では節分だけでなくえびす講や初午など、寒い季節の行事でけんちん汁が食べられていたんだって。節分で食されるのは、その名残のようです。
けんちん汁の発祥にも、複数の説が。その1つは、鎌倉の建長寺で修行僧がつくった精進料理が元祖で、けんちょう汁→けんちん汁と呼ばれるようになった……というもの。ほかに、普茶料理(中国版精進料理)である「巻繊(ケンチェン)」が語源という説も。
立春を前に、精進料理で背筋を正す……と考えると、“節分けんちん”って、なかなかナイスな行事食じゃないでしょうか?
シャチョーくんのこんにゃく工場がある日光では、“節分けんちん”の風習はあまり聞きませんが、カラダとココロを温めてくれるけんちん汁は、2月にぴったり。みなさんも、今年は恵方巻+けんちん汁で、節分ディナーをお楽しみアレ♥
もちろん、“節分けんちん”にはこんにゃくたっぷりで、“砂おろし”も忘れずに〜♪
【オススメ記事】
愛媛では、ハレの日にも蒟蒻!
願い別☆開運蒟蒻メニュー
庶民の蒟蒻愛は、江戸時代から