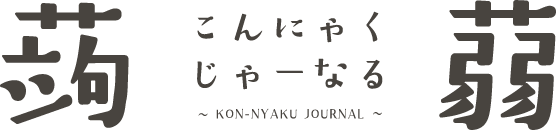[こんにゃくWord 学習帳]
蒟蒻歳時記
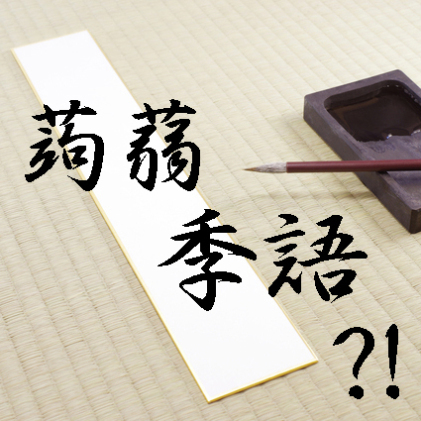
松尾芭蕉がこんにゃくをこよなく愛したのは、以前ご紹介した通り。芭蕉は食品としてこんにゃくを詠みました(つまりシーズンレス)が、植物としてこんにゃくを扱うと、季語になるんデス。今回は、“蒟蒻季語”をご紹介〜♪

晩春「蒟蒻植う」
こんにゃく芋を植えるのは、4月下旬から5月はじめ頃。そのため、晩春の季語とされています。

初夏「蒟蒻の花」
成長の早いこんにゃく芋は、植え付けからグングン成長し、5月下旬頃に花を見せてくれます(ただし5年ほど経った一部の芋に限る)。花と言っても、こんにゃく芋の場合、ちょっとグロ。でも、どことなくトロピカルで夏に似合うかも…?
噂によると、花言葉は「柔軟」デス。明らかに花じゃなくぷるぷる食品としての“こんにゃく”からの連想ですが(汗)、この花言葉、本当なんでしょうか…。
初冬「蒟蒻掘る」
葉が朽ちた10月下旬から11月上旬は、収穫時期! 「蒟蒻掘る」を筆頭に、「蒟蒻玉」「蒟蒻玉掘る」「蒟蒻(玉)干す」などがこの時期の季語に。
俳句界でもっとも権威ある賞とされる「蛇笏賞」を受賞したエラ〜い俳人・津田清子も「日蔭育ちの蒟蒻芋を掘りころがす」と詠んでいるんですヨ。
晩冬「蒟蒻氷らす」
こんにゃく芋がすでに収穫されてしまった冬にも、「蒟蒻氷らす」「氷蒟蒻」「氷蒟蒻造る」なーんて季語が。
実は「氷蒟蒻」とは、以前紹介した凍みこんにゃくのこと。晩冬、農閑期の田畑にワラを敷きつめてこんにゃくを並べ、夜に凍りつき・昼に解凍される…を繰り返すことで、カラッカラで味染み◎の凍みこんにゃくが出来上がるんです。
今や絶滅危惧種の食材ですが、戦前は各地で食されていたそうなので、季語として使われたのでしょう。
さてこんにゃく季語のレクチャーが終ったところで、しゃちょーくんが一句…。
蒟蒻植う
板へと延べる
日を夢見
[自主解説]
こんにゃくに加工できるのは、一般的に3年生の芋から。1年生からはじめると、なかなか長〜い道のりなんです。
その分、板こんにゃくにできる日が待ち遠しい! 金の延べ棒の大もとは、金鉱石。板こんにゃくのもとは、こんにゃく玉♥︎